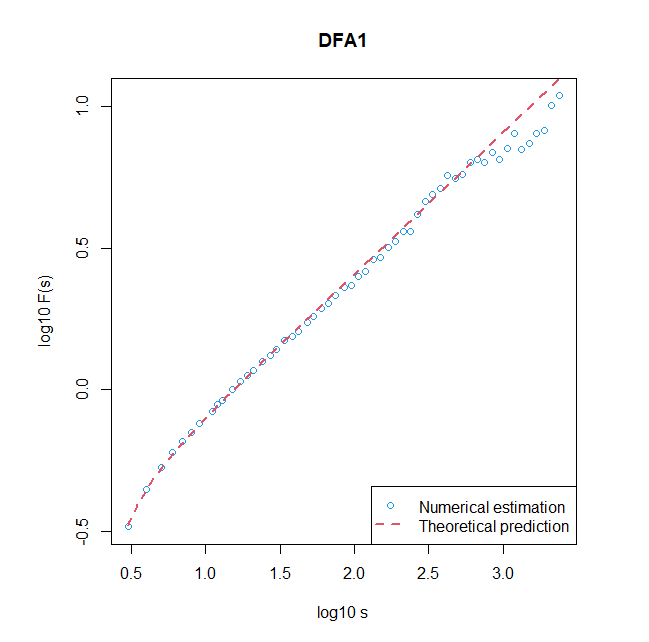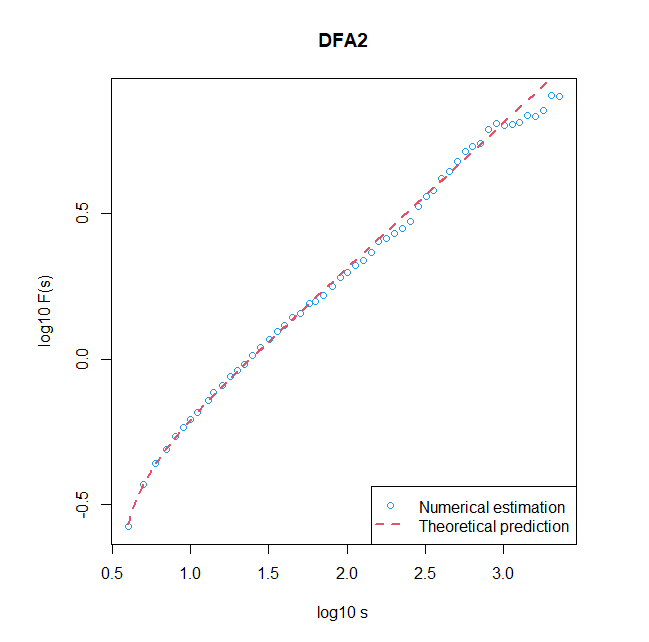北川先生の本「Rによる 時系列モデリング入門」で,Householder変換を使った最小2乗フィットの話が登場したので,Rでやってみます.
ここでは,以下の式を使ってデータを生成します.

ここで, は,平均0,標準偏差
は,平均0,標準偏差sd.epsの正規乱数とします.
以下のスクリプトでは,データの長さをN,パラメタ を
をa1, を
をa2に設定します.

と表せば,

です.ベクトルはすべて縦書きの列ベクトルとします.
逆行列を使った最小2乗法
残差としての の2乗和が最小になるように
の2乗和が最小になるように  を計算すると,
を計算すると,

となります. は,
は, の転置行列を表します.説明は,過去の記事を参考にしてください.
の転置行列を表します.説明は,過去の記事を参考にしてください.
chaos-kiyono.hatenablog.com
以下は,N = 10,a1 = 2.4,a2 = -3.0とした例です.Rのコマンドを使って逆行列を計算して,パラメタを推定しています.
# データの長さ
N <- 10
# 誤差の標準偏差
sd.eps <- 1
eps <- rnorm(N,0,sd.eps)
##############################
a1 <- 2.4
a2 <- -3.0
##############################
# 真のモデルは
# y[i] = a1 * x1[i] + a2 * x2[i] + eps[i]
##############################
x1 <- rnorm(N,0,1)
x2 <- rnorm(N,0,1)
y <- a1*x1+a2*x2+eps
##############################
Y <- matrix(y[1:N], ncol=1) # ncolで列数のみ指定
Z <- matrix(c(x1[1:N],x2[1:N]), ncol=2)
##############################
# a.hat = (t(Z) Z)^{-1} t(Z) Y
##############################
a.hat <- solve(t(Z) %*% Z) %*% (t(Z) %*% Y)
# 残差の2乗平均
sig2.hat <- sum((Y - Z %*% a.hat)^2)/nrow(Y)
# a1, a2の推定結果
a.hat[,1]
# 残差の2乗平均 sig2
sig2.hat このスクリプトを実行すると,
> # a1, a2の推定結果
> a.hat[,1]
[1] 2.425303 -3.634048
> # 残差の2乗平均 sig2
> sig2.hat
[1] 1.607804
のように,パラメタと残差が計算されます.
QR分解 (Householder変換)を使った最小2乗法
次は,QR分解 (Householder変換)でパラメタを推定してみます.pracmaパッケージを使いました.最初に,このパッケージをインストールしてください.
使ったRスクリプトは以下です.
#install.packages("pracma")
require(pracma)
# データの長さ
N <- 10
# 誤差の標準偏差
sd.eps <- 1
eps <- rnorm(N,0,sd.eps)
##############################
a1 <- 2.4
a2 <- -3.0
##############################
# 真のモデルは
# y[i] = a1 * x1[i] + a2 * x2[i] + eps[i]
##############################
x1 <- rnorm(N,0,1)
x2 <- rnorm(N,0,1)
y <- a1*x1+a2*x2+eps
##############################
Y <- matrix(y[1:N], ncol=1) # ncolで列数のみ指定
Z <- matrix(c(x1[1:N],x2[1:N]), ncol=2)
###
# X = [Z|Y] と結合
X <- cbind(Z,Y)
##############################
# Householder変換
UX <- householder(X)$R
###
m <- ncol(UX)-1
a.hat <- numeric(m)
a.hat[m] <- UX[m,m+1]/UX[m,m]
for(i in 2:m){
a.hat[m+1-i] <- (UX[m+1-i,m+1]-a.hat[(m+2-i):m] %*% UX[m+1-i,((m+2-i)):m])/UX[m+1-i,m+1-i]
}
# 残差の2乗平均
sig2.hat <- UX[3,3]^2/nrow(Y)
# a1, a2の推定結果
a.hat
# 残差の2乗平均 sig2
sig2.hat このスクリプトを実行すると,
> # a1, a2の推定結果
> a.hat
[1] 2.611575 -2.950162
> # 残差の2乗平均 sig2
> sig2.hat
[1] 0.6768868
のように,パラメタと残差が計算されます.
pracmaパッケージを使わなくても,Rのコマンドqrを使えば,QR分解できます.中身のアルゴリズムについては,何を使っているのか分かりません.Rスクリプトは以下です.
# データの長さ
N <- 10
# 誤差の標準偏差
sd.eps <- 1
eps <- rnorm(N,0,sd.eps)
##############################
a1 <- 2.4
a2 <- -3.0
##############################
# 真のモデルは
# y[i] = a1 * x1[i] + a2 * x2[i] + eps[i]
##############################
x1 <- rnorm(N,0,1)
x2 <- rnorm(N,0,1)
y <- a1*x1+a2*x2+eps
##############################
Y <- matrix(y[1:N], ncol=1) # ncolで列数のみ指定
Z <- matrix(c(x1[1:N],x2[1:N]), ncol=2)
###
# X = [Z|Y] と結合
X <- cbind(Z,Y)
##############################
# QR分解でRを求める
UX <- qr.R(qr(X))
###
m <- ncol(UX)-1
a.hat <- numeric(m)
a.hat[m] <- UX[m,m+1]/UX[m,m]
for(i in 2:m){
a.hat[m+1-i] <- (UX[m+1-i,m+1]-a.hat[(m+2-i):m] %*% UX[m+1-i,((m+2-i)):m])/UX[m+1-i,m+1-i]
}
# 残差の2乗平均
sig2.hat <- UX[3,3]^2/nrow(Y)
# a1, a2の推定結果
a.hat
# 残差の2乗平均 sig2
sig2.hat
まとめ
QR分解について,勉強してみてください.QR分解の方法には,グラム・シュミットの正規直交化法とか,Householder変換を使う方法とか,ギブンス回転を使う方法などがあるそうです.
【付録】3変数の場合
逆行列を使う場合.
N <- 10
sig2 <- 1
eps <- rnorm(N,0,sqrt(sig2))
##############################
a1 <- 2.4
a2 <- -3.0
a3 <- -1.8
##############################
# 真のモデルは
# y[i] = a1 * x1[i] + a2 * x2[i] + a3 * x3[i] + eps[i]
##############################
x1 <- rnorm(N,0,1)
x2 <- rnorm(N,0,1)
x3 <- rnorm(N,0,1)
y <- a1*x1+a2*x2+a3*x3+eps
##############################
Y <- matrix(y[1:N], ncol=1) # ncolで列数のみ指定
Z <- matrix(c(x1[1:N],x2[1:N],x3[1:N]), ncol=3)
##############################
# a.hat = (t(Z) Z)^{-1} t(Z) Y
##############################
a.hat <- solve(t(Z) %*% Z) %*% (t(Z) %*% Y)
# 残差の2乗平均
sig2.hat <- sum((Y - Z %*% a.hat)^2)/nrow(Y)
# a1, a2の推定結果
a.hat[,1]
# 残差の2乗平均 sig2
sig2.hat Householder変換を使う場合.
#install.packages("pracma")
require(pracma)
###############
N <- 10
sig2 <- 1
eps <- rnorm(N,0,sqrt(sig2))
##############################
a1 <- 2.4
a2 <- -3.0
a3 <- -1.8
##############################
# 真のモデルは
# y[i] = a1 * x1[i] + a2 * x2[i] + a3 * x3[i] + eps[i]
##############################
x1 <- rnorm(N,0,1)
x2 <- rnorm(N,0,1)
x3 <- rnorm(N,0,1)
y <- a1*x1+a2*x2+a3*x3+eps
##############################
Y <- matrix(y[1:N], ncol=1) # ncolで列数のみ指定
Z <- matrix(c(x1[1:N],x2[1:N],x3[1:N]), ncol=3)
##############################
# X = [Z|Y] と結合
X <- cbind(Z,Y)
##############################
# Householder変換
UX <- householder(X)$R
###
m <- ncol(UX)-1
a.hat <- numeric(m)
a.hat[m] <- UX[m,m+1]/UX[m,m]
for(i in 2:m){
a.hat[m+1-i] <- (UX[m+1-i,m+1]-a.hat[(m+2-i):m] %*% UX[m+1-i,((m+2-i)):m])/UX[m+1-i,m+1-i]
}
# 残差の2乗平均
sig2.hat <- UX[3,3]^2/nrow(Y)
# a1, a2の推定結果
a.hat
# 残差の2乗平均 sig2
sig2.hat
の瞬間にいろんなことが起こりすぎてややこしいです.私としては,まず下の図の下段のように考えて,それを
に閉じ込めたとみなしたいです.

は正の定数,
は下の図のように定義します.

として,
の
を変えて,数値的に解いた結果が下の図です.ピンクの部分が
,青の線が応答(出力)
で,
を0に近づけています.

とした結果を考えています.以下では,
としたものを,
として,
の関数を含む式)です.この方程式の一般解は,同次(斉次)方程式(外部からの入力を表す
の関数がない式)
と,右辺に
を含む非同次方程式の特解
の和で与えられます.なぜなら,
と
は,それぞれ,
と
は定数で,
です.
を,
の関数
に変えちゃいます.つまり,
を非同次方程式に代入し,
を求めます.
の面積を,
の領域に置いているので,
に対して,
は,一般解に対応するので無視すれば,特解が
を定数として,
を満たすように
を設定すれば (
),
に対する応答は,
で生じています.
にインパルスを与えたと考えると,変な感じがします.ですので,私は
で,
が0に近い時刻でインパルスを入れたとみなしたいのです.
です.
を微分方程式の両辺にかけると,
のラプラス変換を
とします.微分方程式の両辺をラプラス変換すると,
を使うと,
は単位ステップ関数
とすると,
になって,初期条件
を満たさなくなってしまします.明らかにダメです.
の一瞬をどうとらえるかです.私としては,
の瞬間にすべてが起きたと考えるのではなく,
の直後の無限に短い時間の間に応答が生じたと考えたいということです.